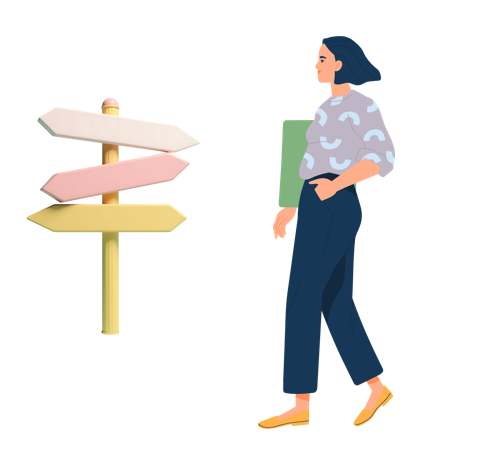
A・M
第3事業部
エンターテインメントソリューション部
A・Mは、大学では日本史を専攻しましたが、「新しいことが学べる」という期待からIT業界を志望しました。
「大学時代は歴史や人文系への関心が強かったので、就職するのなら、それまでまったく意識してこなかった仕事に就いてみたいと考えました。IT業界を志望したのは、デジタル化が世の中全体で進んでいて、その動きはこの先も止まることがないだろうから新しい経験をいろいろできるだろうと考えたのと、ITの知識は仕事以外でも必要になると思ったことが動機でした」
A・Mは当社への就職が決まってから、入社前に独学でPythonを勉強しています。そのときに「コーディングの組み立て方は、人文系で重視されている論理の組み立て方に似ているという感想をもちました」と言います。
半年間にわたる新入社員研修の中では、Javaを学びました。座学と実習による研修でしたが、「この仕事は自分に合っている」という感触を得たそうです。
「友人の中にコンピュータサイエンスを専攻しているのがいて、その友人からプログラミングはかなりハードな世界だよと聞かされていたので身構えていたのですが、研修を受けてみるととても楽しく、プログラミングの面白さに惹かれるものがありました。そのときの感覚は、入社して2年半経った今も続いています」
新入社員研修の後、大手旅行代理店のシステムを保守・開発するチームへ配属されました。そこで画面周りとサーバー双方のプログラムを修正・拡張する保守の仕事を1年ほど続けました。そして現在は、それに加えて、改修のための設計の仕事も担当するようになっています。
「自分で考えながら作ったシステムが実際に動いて、それを触って機能していることを実感できるのは、この仕事の醍醐味の1つだと感じています。上司は、私が新しい仕事を少しずつ経験できるようにマネジメントしてくださっているので、私なりの達成感と成功体験を積み上げながら仕事をしています」
A・Mのチームでは最近、保守・開発作業にMicrosoft Copilotを使うようになりました。生成AIを利用するコーディングアシスタントで、さまざまな作業の効率化に役立っていますが、A・Mは次のような点に気づくようになったと話します。
「Copilotはプロンプトがうまく作用すると、驚くほど短時間に正確なコードを生成してくれます。ただし、そうならない場合も多く、ちょっとおかしいと思えるコードを吐き出してくることもあります。
その経験から思うのは、プロンプトの立て方と、生成してくるコードの正確性を読み取るスキルや経験の重要性です。そして、これからは“がむしゃら”にコードを書くのではなく、それよりもプログラムの正確性と価値を読み取る読解力のほうがより重要になるということです。今後はそうしたことを頭の隅に置いて、保守・開発の作業をしていきたいと考えています」
A・Mが所属するチームでは、開発手法としてスクラムを採用しています。少人数のチームで短期間に開発を繰り返しシステムを作り上げる手法ですが、この開発手法ではチームワークとコミュニケーションが欠かせません。A・Mのチームでは、週に3日、それぞれ30分ずつミーティングを開催しています。
A・Mのチームには、A・Mより後輩の同僚とプログラミングが未経験の若いビジネスパートナーのエンジニアがいます。
「後輩たちに対しては何かを教えるというよりは、お互いに知っていることを教え合う、共有し合うという感じで仕事をしています。
私は、自分のキャリアプランを具体的にもっていませんが、チームのメンバーがより働きやすくなるようなチームの運営には魅力を感じています。
私は大学時代にイングリッシュ・ハンドベルのサークルに所属していました。そこで指揮を担当する時期もありましたが、そのときに、ちょっとしたアイコンタクトを送り合うだけでチームの演奏が見違えるように変わっていく経験をしました。それは今の仕事にも通じることだと感じています」
My Hobby・My Interest
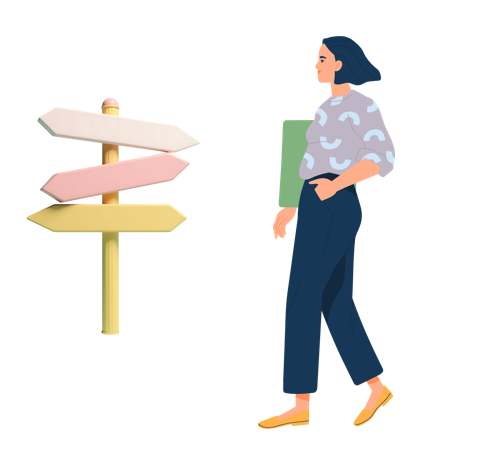
歩くことと旅行が好きで、旅先で昔の名残りを留めた街並みや建物などを見て歩くのが好きです。またその土地の博物館や資料館めぐりをするのも楽しみで、探し出しては訪れています。

