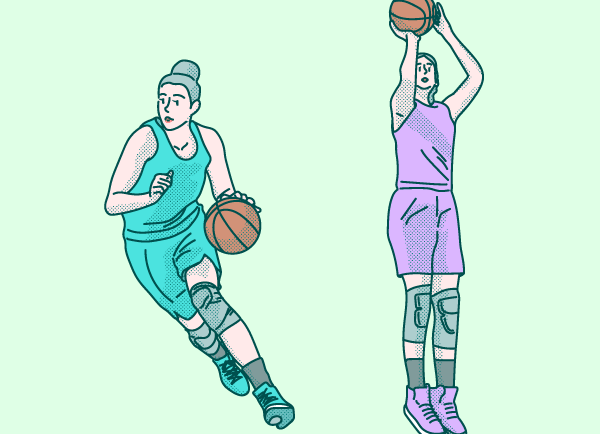丹尾 隆
第4事業部
事業部長
ーー 第4事業部は、お客様の業種や提供しているサービスの種類でみると、実に多様で幅広いですね。
丹尾 IBM iとそれ以外が半々の割合ですが、システム開発からお客様サイトでの運用・保守、各種ご支援までいろいろ担当させてもらっています。
ーー そうした中で短期・中期・長期の目標とミッションは何ですか。
丹尾 1つは、IBM iビジネスを大きく伸ばすことです。IBM iに関してはさまざまな強みを従来から持っていますが、それらを戦略的に強化しビジネスを飛躍させようという計画です。そのことは3カ年の中期経営計画として取り組んでいます。
もう1つは、システム開発案件が多くを占めるので、開発の品質を保持しつつ、それをどう効率化するかが大きなテーマです。
ーー 最近のIBM iビジネスのトピックは何ですか。
丹尾 メインフレームからIBM iへのコンバージョン案件を新規に受注し、プロジェクトを進めていることです。コンバージョンについてはこれまでも手がけたことはありますが、最近は少々様相が違ってきて、お客様からのお問い合わせや引き合いがコンスタントにあります。
その背景には、国産メーカーがメインフレーム事業からの撤退を表明したり、IBM iへ移行したほうがコストやシステムの柔軟性などでメリットが多いという判断があるのだと思いますが、この先もメインフレームからの移行案件には積極的に関わり、力を入れていくつもりです。
ーー そのほかはどうですか。
丹尾 もう1つ、お問い合わせや引き合いが多いのは、古いIBM iシステムをオープン系技術を使って作り直すモダナイゼーションの案件です。IBM iをバックエンドとし、フロントエンドをPHPやJavaで構築する大規模プロジェクトが進んでいます。こうした案件は、これからも増えていくだろうと見ています。
ーー 目標の2つ目に挙げた、開発の効率化についてはどのように取り組んでいますか。
丹尾 これについては2つの側面で取り組んでいます。1つは人材の育成、もう1つは生成AI技術の活用です。IBM iの案件はこれからも増えていくでしょう。けれども、それに合わせてコンスタントにIBM i技術者を増やしていくのは困難です。そうなると、今いるエンジニアのスキル・能力を高めるか、ほかの手段を考えるしかありません。そのほかの手段で今最も有力なのは、生成AIだろうと思います。
ーー どのように生成AIを活用するのですか。
丹尾 具体的な取り組みはこれからですが、お客様プロジェクトの中で試しているのは、お客様の資料やデータを当社開発の生成AI(ChatCube)で学習させて、開発作業を効率化しようというものです。スピーディな検索や情報の確認が今のところの用途ですが、メンバーからは「かなり使える」という評価を得ています。お客様の古いコードの説明や、古いコードから新しいコードへの変換、コードの生成などはこれからですが、時流に遅れず、時流をリードする気持ちで考えています。
ーー IBM i技術者の育成についてはどのような考えですか。
丹尾 具体的に進めているのは、Javaなどをやってきたオープン系の技術者にIBM iを習得してもらい、プロジェクトに入ってもらうことです。これの実績はすでにあり、この路線の拡大がテーマの1つです。オープン系エンジニアには、当社のJ CUBEアカデミーでIBM iを習得してもらい、戦力化しています。
またIBM iシステムの支援といっても、IBM iだけわかっていればよいのではないので、IBM i技術者にも他の技術を習得する機会を設けています。
とはいえ、それらは一朝一夕にできることではないので、IBM i技術者とオープン系技術者をメンバーとするチーム編成も積極的に進めています。それが臨機応変にできるのも、オープン系技術者とIBM i技術者が多数いる当社の強みだろうと思います。
ーー IBM iのお客様の状況をどう見ていますか。
丹尾 IBM iのお客様は本当にいろいろな問題を抱えています。その中で特に深刻なのは要員不足と高齢化で、スキルの不足や新しい技術への対応も大きな課題です。そしてそれらがネックとなって、新しいシステム・チャレンジが生まれてこないのも事実だろうと思います。
ーー それに対して、第4事業部ではどのようなサービスを提供しているのですか。
丹尾 どのようなお困り事に対しても、対応させていただくというのが基本スタンスです。IBM iは非常に優れたプラットフォームです。そしてその上にはお客様の貴重なシステム資産が築かれています。その資産を活用しつつ将来へつなげていくのがお客様の最大のメリットですので、そのためのご支援を、オンプレミス/クラウドの両面で、基盤からアプリケーション、サービスに至るまでオールラウンドでご用意しています。
お困り事や新しいシステム課題がありましたら、まずは当社にお声がけいただければと思います。お客様の今後のヒントになるお話やご提案ができると考えています。